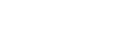July 07, 2013
LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲 著者:シェリル・サンドバーグ
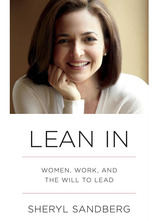 LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲
LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲著者:シェリル・サンドバーグ
日本経済新聞出版社(2013-06-26)
Facebook COOであるシェリル・サンドバーグさんの本[LEAN IN] (リーン・イン)を読んだ。
仕事に対する考え方は、だいたい同じだね。
月曜から金曜も土日のように直截的でリラックスして本音で話すこと。
社内説明でPPTなど必要ない。メモもいらない。ただ、簡潔に話し合えればそれでいい。
そういうフラットな立場に身をおいて物事をみると正しい方向が見えてくるんだ。
tabloid_007 at 15:46|Permalink│Comments(0)│
May 12, 2013
【不眠の森を駆け抜けて】 (ラピュタBOOKシリーズ) 著者:白坂依志夫
 不眠の森を駆け抜けて (ラピュタBOOKシリーズ)
不眠の森を駆け抜けて (ラピュタBOOKシリーズ)著者:白坂依志夫
ふゅーじょんぷろだくと(2013-05-11)
出版社[ふゅーじょんぷろだくと]の才谷社長から、シナリオライターの大御所 白坂依志夫さんの半生を描いた本の出版記念パーティに呼んで頂いた...のに行けなかった。
三島由紀夫や大江健三郎との親交も"らしい"エピソードで面白いが、やはり、いつも目ヤニを付けた安倍公房氏との僅かなエピソードを知ることが出来て良かった。
安倍公房の熱狂的なファンとしては、白坂さんが芥川賞をとったにもかかわらず極貧だったデビュー時代と体調不良の晩年の様子。
この積年の長さを僅かな描写で知ることができただけでも読む価値ある。
tabloid_007 at 18:38|Permalink│Comments(0)│
February 03, 2013
本【山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた】不幸を幸福と感じるチカラ
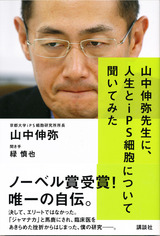 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた著者:山中 伸弥
講談社(2012-10-11)
ノーヘル賞に関心はないが、関西人の活躍には関心がある。
最近は、小説より人の話に興味がある。だからそういう観点で読んでみた。
まず、山中教授が医学部を卒業した1987年に整形外科の研修医として勤務するが、あまりにも手術に時間がかかり「ジャマナカ」と揶揄されていたらしい。その時代を通じて中国の故事「人間万事塞翁が馬」(じんかん ばんじ さいおうの うま)を実感する。
一件、不幸と思うことも幸福のはじまりかもしらん、という発想。こういう苦しい時こそ、直観的に未来を信じる力というのが成功の秘訣なんだな。
tabloid_007 at 11:44|Permalink│Comments(0)│
January 10, 2013
安部公房の未発表短編「天使」(昭和21年)が発見された!
 新潮 2012年 12月号 [雑誌]
新潮 2012年 12月号 [雑誌]
新潮社(2012-11-07)
小説家 安部公房が終戦直後の昭和21年秋、22歳で書いた未発表の短編小説が昨年見つかった。北海道に住む安部の実弟、井村春光さんが自宅に保管していた。それが文芸誌「新潮」12月号に全文が掲載されるや瞬く間に完売。
異例の増刷をしたという。
短編は「天使」という題で、A5判ノート19枚に黒インクで書かれていた。旧満州から日本への引き揚げ船内という過酷な環境下で執筆されたらしい。
安部の3作目の小説になる。左右の行を空け、横書きノートに縦書きしていくスタイルは初期の自筆原稿と同じで、安部の長女、安部ねりさん(58)が安部の青年期の筆跡であると確認した。保管していた井村さんは文学への関心が強く、安部が発表前の作品をよく見せていたという。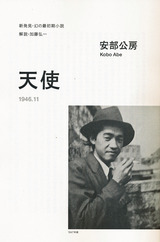
精神病院を抜け出した「私」の1日の物語。
人間を天使だと思い込む妄想を抱く男が主人公。通行人や看護人ら外界のすべてが天使に見え、自らをも天使と認識していく。
主人公が病室を見て、<固い冷い壁だと思っていたものが、実は無限そのもの>であったと語る場面にその後の「壁」を彷彿とさせる。
最後のセンテンスが実にポエティックである。
「記憶以前の記憶を呼び覚まされた様な懐かしさに、誘われる様になって私は垣ぞいに歌の聞えて来るその窓辺に近付いて行った。」
tabloid_007 at 21:32|Permalink│Comments(0)│
December 30, 2012
【高倉健インタヴューズ】(著者 野地 秩嘉):達人の“気”は日々の努力で発することができる!
 高倉健インタヴューズ
高倉健インタヴューズ著者:野地 秩嘉
プレジデント社(2012-08-10)
最近は、あまり小説とか読まない。クリエイターの本か自伝かインタビューを読む。
だから、特別 高倉健さんの映画をたくさん見ているわけでもない。
滅多に自分を語らないといわれている健さんの実像に迫るため、著者がほうぼうのインタビューを集めてきて一冊にまとめたものだ。
だから、体系的に語られているわけではないが、逆に断片的だから面白い。
高倉健さんが日々やってることは、好きな仕事を一流にしようということに尽きる。
新しい映画を見に行く。映画の原作になりそうな本や送られてきた脚本を読む。いつでも映画に出られるように肉体を訓練する。ロケでは体調を守るため現地のものを食さず、レトルトカレーを持参する。自分の出番でない時も現場にいて、決して椅子に座らず見守っている。
すべて映画に映るために鍛錬を積んでいる。付き人もおらず自分で出向き、自分で話し、去っていく。実にカッコいい大人なのである。
本の中で、1959年に結婚した江利チエミさんとのエピソードが微笑ましい。
生まれて初めて買った新車のベンツが等々力の自宅に納車された。
「夜中の一時ごろでしたか、のせて走ったんです。そしたら、途中で降ろしてくれって言うんです。あなたが走ってるところが見たいから、って。で、ぼくがやつの目の前を行ったり来たり走るんです。そしたらあいつ拍手してくれるんですよ。かっこいいよ!って。可愛いなあと思いました。この女のためならなんでもできるなあと」
健さんは、その後独身を貫き、彼女の命日には墓参りするという。
素敵な話だなぁ。
tabloid_007 at 10:11|Permalink│Comments(0)│
December 09, 2012
本【PRESENT プレゼント 世界で1番大切なことの見つけかた】(著者 坂之上洋子):自分の中に眠っている“とっても良い自分”を再発見するために…
 PRESENT プレゼント 世界で1番大切なことの見つけかた
PRESENT プレゼント 世界で1番大切なことの見つけかた著者:坂之上洋子
メディアファクトリー(2012-12-07)
以下、よーこさんの本を読みながら、頭をよぎった雑念をメモにしてみた。
まとまりないげと、この本にも中途半端でいいって書いてある。
考えてみたら、人生はビジネスみたいにある期間の中で成果を出す必要がない。
ぶらり旅みたいなものなんだ。
だから成功した人生とか失敗した人生なんていうのは、そもそもない。
大人になればなるほど、自分で自由に考えて物事を決められるからね。
食べたものは、1日くらいで循環して体内からでていってしまうが、楽しい記憶も、苦しい記憶も、何気ない記憶も決して自分の中から消え去るものではない。
ぶらり旅みたいなものなんだ。
だから成功した人生とか失敗した人生なんていうのは、そもそもない。
大人になればなるほど、自分で自由に考えて物事を決められるからね。
食べたものは、1日くらいで循環して体内からでていってしまうが、楽しい記憶も、苦しい記憶も、何気ない記憶も決して自分の中から消え去るものではない。
いつも覚えていられる訳じゃないが、ある日突然 のっと顔をだしたりする。
どこにストックされていたのか、それらの過去の断片が、自分という生き物を形作っているんだろうな。
過去の記憶が、現在の自分にああしろこうしろって言ってるのだ。
それは、過去から自分へのギフトなんだと思う。
歳を重ねるごとに優しくなれるとすれば、それはそうした記憶のエンジェルのおかげかもしれない。同数の老人と同数の若者を比較して調査したら、きっと老人の優しい指数が勝っていると思う。経験の差は優しさの差である。きっと。
だから成熟した大人の役割は、社会に対して“優しさ”を供給することにあるのだ。
だから成熟した大人の役割は、社会に対して“優しさ”を供給することにあるのだ。
“怒れる”のは若者だけでいい。そういう怒りのエンジンも社会には必要だろう。
大人が優しさを提供すめためには、それまでの人生で人とたくさん話して、たくさん考えて、たくさん頭をぶつけなけりゃならない。
そういう記憶の蓄積が優しさに転化する。悪事や狡猾な利用のされ方では困るのだ。怒りが優しさに勝つような社会では大人の負けなんだな。
よーこさんは、そうならないように 生き方のコツみたいなものを伝授してくれている。
本書は、誰かへのギフトというのではなく、自分の中に眠っている“とっても良い自分”を再発見するための指南書なんじゃないかなぁ。その発見こそが自分への最大の“プレゼント”なのだろう。
tabloid_007 at 21:51|Permalink│Comments(0)│
December 08, 2012
【人間が好き―アマゾン先住民からの伝言】(写真・文 長倉 洋海) “鳥のように 静かに地上におりたち 静かに飛び去っていく”生き方
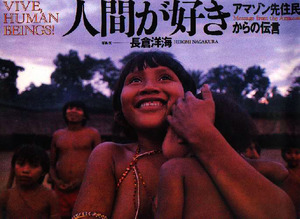 人間が好き―アマゾン先住民からの伝言
人間が好き―アマゾン先住民からの伝言著者:長倉 洋海
福音館書店(1996-10)
フェイズブックでNPO「えほんうた・あそびうた」西村直人さんから教えてもらった本が届いた。
アマゾンの村では「お腹がすけば、森に入って果物を食べ、暑ければ、小川で水浴び」をする。
「森があれば生きていける。子孫には森のほかには、財産は残しません」
そして
「楽しく踊り、幸せになるために、生きている」という。
このような長閑な田舎暮らしの様子が素敵な写真とキャプションで紹介される。
だが、そんな人間本来の暮らし向きにノスタルジアを感じるだけの本ではなかった。
ここには、社会で対立や問題があった時の対処法が書いてある。
「村どうしの対立があったときは、丸太かつぎ競争をします。勝ち負けが決まれば、それ以上は争いません。」
この原則・ルールにしびれる。単純だが、もっとも合理的な解決法のように思えるのだ。都会に住んで文明が進めば、それでいいのか?昔に戻った生活などできないが、考え方はリセットできる。
アラブとイスラエルの問題。子どもに聞かれたらどう答えられるのか?
こんな単純なバカげたことも解決できない現代人って...何を学んできたのか?
そうなんだ。丸太かつぎ競争だよ。勝ち負けがハッキリしたら喧嘩はおしまい!
そういう社会に少しでもできるように行動しよう、考えよう。一人一人が考えたこと、考えに基づいて行動したこと。それが殺し合いに勝てる唯一の方法と思う。
tabloid_007 at 15:48|Permalink│Comments(0)│
November 25, 2012
コラム【ソーシャルもうええねん】(著者 村上福之): 流行の「ソーシャル」と関西弁否定形の「もうえぇねん」を組み合わせることで、クワっとしたオーラを発している本!
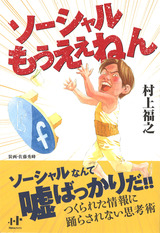 ソーシャルもうええねん (Nanaブックス)
ソーシャルもうええねん (Nanaブックス)著者:村上福之
ナナ・コーポレート・コミュニケーション(2012-10-26)
タイトル買いだった。
流行の「ソーシャル」と関西弁否定形の「もうええねん」を組み合わせることで、クワっとしたオーラを発している!笑
ネット上で買えるSNSの価格表が面白い。
YouTube 再生数5,000回で2,300円 0.46円/人
Twitterのフォロワーは5千人分で3800円。 0.76円/人
Facebook「いいね」5千人分で15,000円。 3.00円/人
ほとんど、アメリカの業者と思うが、中身(クリックした後の回遊率)とか無視で単に“数”の獲得の話である。
ただ、この中で媒体にとっての価値が広告収入となると、YouTube以外収入の当所がないので、増やす意味というのは、「オレ、凄いだろう!エヘン!!」以外ないのが笑える!
YouTubeの広告アフィリエーション収入にしたって、1再生0.1円くらいだから、0.46円もコストをかけている段階で差分広告収入はないのだ!だから、やはり「エヘン」目的だろう。
あと本書で参考になったのは、プロジェクトが佳境になればなるほど、会って打ち合わせした方が良いと説いているところ。
これは、よくわかる。
そこには「単純接触の法則」が働いているという。単純に何度も接触したものにいい印象を抱くという法則らしい。テレビCMを頻繁に見ているだけで欲しくなるのも同様のことだ。だから、接触時間ではなく、あくまで頻度、接触回数。
これって仕事だけじゃなく、プライベートにも応用できるかもね!
IT業界以外の人にもお勧めです。
tabloid_007 at 17:38|Permalink│Comments(0)│
November 24, 2012
コラム【日本人養成講座】(著者三島由紀夫)想像力は、現実が空虚な時に現れる幻のようなものである。
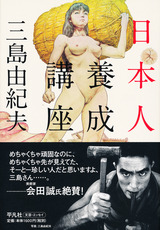 日本人養成講座
日本人養成講座著者:三島由紀夫
平凡社(2012-05-27)
三島由紀夫のコラムは、中高生の時に貪るように読んだ。小説はほとんど読んだことがない。私の三島作品との出会いは、安倍公房である。彼との対談を読んで、なんともふたりの主張が水と油くらいに違うのに、共通の基盤というか知的好奇心を刺激し合う同志のような親密な雰囲気を感じ、読むようになったのだ。
だから、いくつかの小説を読んで自分の好みには合わないのだけれど、コラムや社会批評のようなものは、興味深く読んだものだ。
今回、会田誠さんのブックカバーで新装版がでていたので読んでみた。
以下、記憶に残った個所の抜粋&引用。
・ 西洋では古代や中世以来の石の建築がのこっている。
日本の伝統は、木と紙で出来ていて、火をつければ燃えてしまうし、放置しておけば腐ってしまう。
・西洋ではオリジナルとコピーの間には決定的な差があるが、木造建築の日本では、正確なコピーはオリジンナルと同価値を生じる。
・危急に際して行動に熱中し、生きることのすべての力を注いでいるときには、想像力のほとんどを持つことが出来ない。もし、想像力がノイローゼの原因になるとすれば、空襲にさらされた戦争中の日本だろう。人々の想像力の糧は、すべて戦争という事業に集中していたのである。
・芸道とは何か?それは「死」を以てはじめてなしうることを、生きながら成就する道である、といえよう。これを裏からいうと、芸道とは、不死身の道であり、死なないですむ道であり、死なずにしかも「死」と同じ虚妄の力をふるって、現実を転覆させる道である。
・スポーツにおける勝敗のすべて虚妄であり、オリンピック大会は巨大な虚妄である。それはもっとも花々しい行為と英雄性と意志と決断のフィクション化なのでだ。
・愛という言葉は、日本語ではなく、多分キリスト教からきたものであろう。日本語としては「恋」で十分であり、日本人の情緒的表現の最高のものは「恋」であって「愛」ではない。
以上
tabloid_007 at 00:06|Permalink│Comments(0)│
September 17, 2012
エッセイ【相性】(著者三浦 友和):愛の正体を知りたいと思っていたら、こんなところに“ひょっ”とあった!
 相性
相性著者:三浦 友和
小学館(2011-11-14)
映画「RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ」公開記念に発売された本。
出版の際の報道で、思わずグッとくる三浦さんの言葉があり、即購入した。
「奥様である山口百恵さんが芸能界に復帰したいっていったらどうします?」という聞く側からすれば、何も考えないお決まりの質問だったのかもしれない。
それに対する三浦さんの返答がグッときた。
「もし、結婚31年たって、妻がそんな大きな気持ちを心の奥にしまい込んでいて、自分が気づかなかったのなら。夫失格でしょう。事実だったら失礼な男です。相性云々の前に、離婚しないといけないでしょう。けじめとしてね。」
この“失礼な男です”にグッときた。
愛だよ。これが愛なんだな。いつか正体をみたいと思っていたら、こういうところに“ひょっ”とあったりする。
読んでみたら、その辺の哲学書なんてもう読む必要ないくらい何気ない深さのある本だった。最近、勝新太郎とか芸能人の本を結構読むのだが、サラリーマンと違って保証のない仕事だから、それだけ鋭敏になるし深いわけだよ。
他にも突き刺さる言葉かいっぱいあったな。抜粋すると...
・ 「やさしい人」とは、周囲から評価される人ではなく、他人のことを想像する力をいう。自分の弱さやズルさ、もろさを認めることだと思う。自分のダメな部分がわかってるから、相手の欠点も理解することができる。相手を思いやることができる。それが「やさしさ」だと思うんです。
・ 「相手の言動や振る舞いに対して『自分だったらどうだろう?』と想像できないから、いさかいが起こるんだと思う。簡単に他人を否定する人間は、自分と他人が違う考えをもった人間であることすら気づいてない。
・ 役者の先輩である橋爪功さんから「趣味、何?」ときかれ「陶芸とかやってみたいです」と返答すると「やりなさいよ」と言う。「やりたいと思うことが才能なんだよ」
・ 振り返った時に、プラスとマイナスを換算して、たった1つでもプラスだったら「幸せだ!」と胸を張っていいと思う。マイナスのない、プラスだけの人生なんてあり得ません。
ま、推薦図書だな。
tabloid_007 at 23:04|Permalink│Comments(0)│
August 26, 2012
本【書斎探訪】(著者 宇田川 悟):ノマド時代に書斎の話も悪くない
 書斎探訪
書斎探訪著者:宇田川 悟
河出書房新社(2012-05-17)
ノマドの時代に書斎の話である。
宇田川悟さんが、各界20人の書斎を訪ね、その空間、設計、使い勝手などを質問する。いつもながら、宇田川さんの質問は相手のことを充分に知り尽くした上で、時に控えめに 時に鋭いツッコミをいれる。
相手は待ってましたとばかり 過去の書斎の歴史や設計思想など語ることになる。これは、一見 物書き、クリエイターの仕事場訪問にみえるが、よくよく話を聞くと、書斎の主の脳内そのものの開陳に他ならないことがわかる。
本の場所や資料を探す方法などは、その人の思考回路と同期する。非常に綺麗で生活感のない書斎は見栄っ張りなひと?乱雑に見えて その実 機能的な書斎はロジカルな人?などと邪推してしまう。
インタビュー対象に女性がいないのは、男性の社会性の無さの表れ?もしそうだとすると、話は飛躍するが、引きこもりは昔からあったということなのかもしれない。
子ども部屋の発想自体 男の発想だろう。子ども部屋の概念は1960年代の高度成長期に生活様式が長屋から戸建てになり、核家族化がすすんだことで開発された。
この時に、子ども部屋を与えられた子どもたちがオタク第一世代と思う。部屋では、切手・コイン収集や王冠を集めて見せあって、近所の秘密基地の代替えになった。
その前の世代では若者が大人になるステップに家出というのがあった。家をでると街には悪い兄貴がいて社会の怖さを教えてくれる存在だった。息が詰まる大家族から脱皮でき大人になれた。寺山修司が「書を捨てよ、町へ出よう」といった世代である。
近年30年間の企業姿勢は、子ども達を家にいさせる戦略だったと思う。1983年の任天堂のファミコンは近所の不良のたまり場であったゲームセンターを壊滅させた。映画館はテレビにとってかわられ、DVDやブルレイ、オンデマンドの時代になった。これらの企業メッセージは「家が便利だから、家にいなさい」なのである。だから、ちゃんと引きこもり世代がうまれたのだ。良いか悪いか別として、現代では家出してもたいしてワルはおらず社会勉強にならない。それならば、家をでないで引きこもりながらスマホでもいじってた方がマシってなもんだろう。
つまり書斎の話は立派な大人だけの話じゃなく、発展的な引きこもりの発想にもつながるし、そもそもノマドなどというのも書斎の一形態ではないかと思う。
自分の秘密基地を見直したい方におススメ。
蛇足。
本の中で、結局 書斎があっても、騒々しい近所の喫茶店やファミレスで仕事してます、という意見が多々あり 人間そう簡単に引きこもれないのだなと微笑ましかった。
tabloid_007 at 23:16|Permalink│Comments(0)│
June 17, 2012
本【挑まなければ、得られない】(著者 及川卓也):単に挑んでも何も得られない。挑むべきテーマと検証、あとはユーモアがないと何も得られない。
 挑まなければ、得られない Nothing ventured, nothing gained. (インプレス選書)
挑まなければ、得られない Nothing ventured, nothing gained. (インプレス選書)著者:及川 卓也
インプレスジャパン(2012-05-18)
直接存じ上げませんが....
及川卓也さんというエンジニアの方で、そのブログをまとめた書籍。出張の時に飛行機で読んだ。日本DEC、マイクロソフトを経て、現在はGoogleに在籍されているらしい。
私のように四半世紀以上にわたって娯楽産業で生計をたてている者にとって、エンジニアほど大切な存在はない。特にニューメディア畑を歩んできたので、常に技術の進歩に即してサービスを展開させ、市場を開拓しなければならなかったという事情もある。
1989年に民間最初の通信衛星(CS)を打ち上げた際にも、サービスから間もなく、衛星から軌道とがはずれるという大事件が起きて日本の多チャンネルサービスは困難な船出を経験した。
いまから、8年くらい前にテレビからネットの仕事をやるようになって、もう経営層そのものがテクノロジストということも稀でなくなり、経営と技術の分離など不可能とさえいえる時代になった。
フレームの決まった映画やテレビ業界だと、クリエイターとマーケッターがいればこと足りたのだが、ネットはWINDOWS95にはじまり、現在はワイヤレス、クラウド、スマートフォンなど技術前提でしかサービス開発はないといっても過言ではない。だから、及川さんの経験は非常に大事なのである。
以下、本書から気になった箇所を勝手に要約&抜粋。
・ グラフィックデザインの歴史を俯瞰してみると、新しい技術は必ず新しい美意識を生み出す。
・ バンドをデビューさせるプロデューサーが単純に商業的な成功を考えれば、検索エンジンを意識してネーミングするだろう。
・ 民主的でフェアなリコメンデーションではなくて、作り手の想いを伝えるような推奨やちょっと気の狂ったリコメンの方が新しい発見があっていいのではないだろうか。
・ DRMについて。回し読み文化を維持できるような、つまり家族に読み終わった本を進めるぐらいの緩やかな制御が必要ではないか。
・ 「イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき (Harvard business school press)」(HBSのクレイトン・クリステンセン教授が1997年に発表した概念):企業は既存顧客の声を聞きすぎるあまり、新しい市場の創造を行う新たなライバルに負けることをいう。
・ 自動車産業の父、ヘンリー・フォードの言葉「もし私がカスタマーに何が欲しいか尋ねたら、彼らは『もっと早い馬が欲しい』と言っていたでしょう。顧客の声を聞くのは大切だが、彼らに『何が欲しいか』を聞いても必ずしも答えが出てこない。それよりも彼らの行動をよく観察し、どんなところで苦労しているか、彼らなりにどんな工夫をして今あるものを使いこなしているかを理解した上で、何を創るべきが考えるべきだ」
以上
tabloid_007 at 21:48|Permalink│Comments(1)│
June 03, 2012
対談【中国美女の正体】(宮脇淳子と福島香織):対中国ビジネスの基本姿勢のヒントがいっぱい!
 中国美女の正体 (フォレスト2545新書)
中国美女の正体 (フォレスト2545新書)著者:宮脇淳子、福島香織
フォレスト出版(2012-04-07)
先月は、北京と上海に仕事で行ったのでこの本が役に立った...。というと、女性関係?といぶかしく思われるが、この本は中国女性の生態論を通じて中国という国のキャラクターや歴史を非常に分かりやすく読み解いてくれる対談本なのである。
中国が日本のGDPを抜き世界第二の国家になったことで、日本も中国への関心が以前より高くなっている。しかし実態としては、わかりにくい。
私の感覚的な感想としては、欧米人とのビジネス交渉を経験済みでかつ、以前流行った本じゃないが「NOといえる感性」をもったビジネスマンのみが中国人となんとかやっていけると思う。言うほど簡単じゃないが。
たとえば、中国では二種類のタイプのビジネスマンがいる。一つは「すぐに契約を結びましょう」というタイプ。すぐに契約を結ぶが結局はぜんぜん契約を守らない。不履行ばかり続くのだが、「それは前の担当者の話だから私は知らない」と平気で言う。じゃあ、裁判で決着と考えても、なかなか勝ち目はなかったりする。つまり裁判制度そのもののフェアネス以前に、ビジネスの一作用として契約や訴訟が機能しないのだ。
また一方では、「信頼関係があるのだから契約はいらない」というタイプ。こちらは、ビジネスがはじまるぎりぎりまで値下げ交渉をしてくる。そして、商売がはじまっても一切送金してこない。こういうタイプ。
つまり、どんな優れた日本のビジネスマンでも中国人とビジネスはできないというオチなのである。
しかし、私はいくつかのセキュリティホールを見つけた、と思う。それはここでは記載しないが、まずは、これから中国をめざすビジネスマンに本書を行きの飛行機で読むことをお勧めしたい。
ポイントとしては下記を理解する必要がある...
・ 大陸的な感覚を知ること。間をとる必要は絶対ない。まずギリギリまで詰めてくるが、相手の妥協はない。だからこちらの妥協もない。タクシーではまず相手がいくら出すがきいてくる。相手の言い値は法外である。自分の価値観をしっかり持たないと、まあ安いからいいか、では今後の交渉が思いやられる。私は、絶対自分の言い値(確実に自分の場所とホテルの場所の距離を把握すること)以外妥協せず、駄目なら地下鉄にのった。2元カードにも荷物検査にも慣れている。
・ 2千年に及ぶ儒教の影響で特に北京では男系社会。男に生まれたら勝ち。女性は男の子を産んだら勝ち。それ以外は負け。それでも奥さんは旦那にいつ捨てられるかわかないので、結婚後も旦那の行動をチェック。弱みはいつもメモ。
つい先日も重慶市トップの薄熙来( ボー・シーライ)党委書記が更迭された。あれも、悪妻ゆえの露見とうわさされている。中国のホラー小説の幽霊が必ず奥さんだったりするにはそれなりの訳があるのだ。
・ 中国人は基本的に自分たちを中国人と思っていない。政治的に共和制になっただけだからである。だから地域で北京人だったり上海人と思っている。ただ、唯一自分たちを“中国人”と思うときは日本人の悪口を言っているときである。これは、日本人の政治家がくるだびに謝るから、「毎回、謝るほど悪いことをしたのだ」と思うらしいのだ。市井の人たちと話す感じで反日感情があると思えなかった。
・ 仕事のネットワークは基本は家族。家族の結束は、血縁の結束だけでなく、お金の結束も意味する。中国のツイッターと呼ばれる新浪(シンラン)のCEO曹国偉(チャールズ・チャオ -Charles Chao)は、胡 錦濤(こきんとう フー・チンタオ)の娘婿だったりする。あと、美人は美が権力やお金を生むことを熟知しているので、かつてから西施(せいし)、王昭君(おうしょうくん)、貂蝉(ちょうせん)、楊貴妃(ようきひ)など古代四大美女など国を動かす影響力で権力を動かしていた。
・ 中国は17世紀まで人口1億人いなかった。20世紀の1949年に中華人民共和国ができるまでは、中国よりもっと広い地域を統括する集合体として清朝があった。清朝が五大種族(漢族、満州、モンゴル、チベット、ウイグル)を束ねていたため、宗教と法律と言語を守った。
・ 清朝は、1636年に満洲に建国され、1644年から1912年まで中国を支配した最後の統一王朝。清朝皇帝は、漢人にとっては皇帝だったが、満州人にとっては部族長会議の議長であり、モンゴル人にとってはチンギス・ハーン以来の大ハーンであり、チベット人にとっては仏教の最高施主であり、イスラム教徒にとっては保護者だった。
・この連合国家は、アメリカ大陸の発見によるジャガイモ、トウモロコシなど食糧確保に非常に便利だった。そのことで人口が爆発的に増え、現在の食糧難や部族間対立につながっていくことになる。それでも19世紀には3億人を超え、再び食糧難となり、東南アジアに出向いた人たちが“華僑”とよばれる。華僑の“華”は仮住まいを意味する。それくらいの覚悟で出向いたのだ。
以上、こういう基礎的な話もいっぱい詰まった本書は気軽に中国の感触が確かめられる良書である。ぜひ!
tabloid_007 at 20:39|Permalink│Comments(0)│